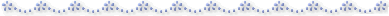June Bride
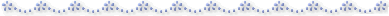
十五
「憂情の森」は、若手劇団「絶対零度」主催者、園山隆史最後の作品だった。
というよりも、園山が引退する最後の公演は、坂城の作品を二人で演出して幕を下ろしたという形だったので、引継ぎの第一作目は、園山の作品を坂城が演出したい、という坂城の意向で、この作品が選ばれたのだ。
園山も坂城も、作品の傾向は似ていた。似ていたからこそ、坂城はこの劇団をまかされた、というのもあるのだが、にもかかわらず、「憂情の森」は少し二人の作風とはトーンの違う作品で、園山自身も書いたものの、ほとんどお蔵入りさせようとしていたのを、坂城がなんとか形に出来ないかとひっぱりだしてきて、わざわざ今度の演目に選んだのだ。
ところが、不得手の分野の作品を選んだのに大当たり、かえって、苦手意識に対抗したのが功を奏した、と言ったところだったのかもしれない。
物語は、十九世紀半ばのヨーロッパ郊外、という設定で、「憂情の森」という名前のつけられた森には伝説がある。元々奥深く迷いやすいが、親に反対された二人が結婚するために飛び込めば、森の番人に会い、祝福されて森を出、幸福になれる、という伝説があった。
物語の主人公シェレンは、恋人リュウと二人で森の中に逃げ込んだが、そこで、森の番人に出会う。ところが、番人は、シェレンの顔を見て、異常なほどに驚き、「エレナではないのか?」と問うのである。そこで、番人の昔語りが始まるのだ。なぜ、番人が、ここで番人をすることになったのか、なぜ、ここが「憂情の森」と呼ばれるようになったのか。
かつて、エレナは森近郊の村の、有力者の娘だった。彼女を置いて村を飛び出した恋人、レイの帰りを待ちつづけていたが、帰ってこない。そのうち、村の土地や彼女の家の財産をねらって、男が彼女に金にもの言わせて接近する。
最初は拒んでいた彼女も、じわじわと周りから結婚せねばいけない状態に追い込まれて行く。やがて、二人の思い出の地である森を工場建設のために破壊するという話が持ち上がり、森を守るために、とうとう婚約するまでになってしまった。ところが、披露パーティーの日になって、レイが帰ってくるのだ。
待っていたシェレンも、待っていた月日で素直にレイを許せない。でも、レイのところに戻りたい。ある日、夜目に紛れて忍んできたレイに、とうとうシェレンは婚約者の元を脱出する決心をする。ところが、その脱出現場を婚約者の男に見られるのだが、男は「そこまで恋しいのなら、行きたまえ」と言って逃がしてしまう。
とうとう、森は工場建設に着手されるかに見えた。ところが、工場主ともどもその土地を撤退、以降、生き残ったこの森は、「憂情の森」と呼ばれるようになったのだ。
森を犠牲にしてエレナは恋に走ったつもりだった。が、男は権力や物欲にモノ言わせていたようで、その影で、本当に欲しかったのは、エレナ自身だったのだ。工場進出は、彼の恋の責め方であったのだ。だから、エレナを行かせた。彼女の大切な、森も残した。そして、彼女を行かせたその婚約者こそが、この森の番人なのだ。
ただ想いを素直に伝えられなかった、哀しい番人の思い出――。
番人の昔語りをきいた後、エレナそっくりだというシェレンは、なぜ、番人になったの? と尋ねる。すると、彼は、「もう誰も、不幸にならないように」と答えるのだ。
ここからラストシーンが始まるのだが、シェレンとエレナが一人二役、婚約者の男の説明とモノローグが終わって、村人達の声が暗転で聞えるという場面の間、エレナからシェレンへと衣装替えをしなければいけない。その時間が約五分。衣装からしても、特に修羅場、というわけでもない。が、クライマックスへと走る大事な場面だけに、失敗は許されないのだ。
今日は通し、というだけあって、間合いを計ることが目的だから、千尋もさほど緊張はしていなかった。それでも珍しく、裏手に坂城が待機しているのは、千尋には始めての経験でもあるからだろう。第一回目の公演の時は、既に千尋は森本の経営する会社「ミル」にうつっていたから、表から公演を見にきただけだった。
前の主役、榎木碧は確かに上手かった。技術が違う。
千尋が今回気をつけたのは、碧が演じた本番に引きずられないことだった。
坂城は、上手くやろうと思うな、と言った。魂で演じろ、と。
そんなこと言われたって、よくわかんないわよ、と心の中で千尋は思っていた。
坂城は、指の先までエレナになることだという。指の先まで――。
舞台の通し稽古で、男のモノローグが始まったのが聞えるのを耳にしながら、衣装換えに裏へと走った。ラストシーンを頭の中に思い描きながら、衣装を換える。
「“ねえ、きいて、おじいさん、私は、エレナよ。エレナが今の話をきいていたら、きっとこう言うと思うの。
『気付かなかったの、あの日は。あなたが本当は、何を、どう考えていたのか。でも、今日やっとわかったの。
今日はじめて、やっと、本当の、あなたに出会えた気がする。ありがとう。』
でももしかしたら、エレナは知っていたのかもしれないわね。知っていて、どうにもならなかったのかもしれない。”」
――知っていても、どうにもならなかったのかもしれない――
手に白いレースを持って、舞台へと戻りながら、脳裏に、柴野の顔が過った。
どうにもならない、運命――運命の女――夢の、女――。
舞台の脇に上がると、ステージは暗転に入ろうとしていた。中央に立った男に当てられたスポットライトが、ほとんど絞られている。番人とレイがあちらから出てくるはずだ、と思っていると、舞台の裾ギリギリに立っている坂城が千尋に視線を投げてきて、投げてきた目がどこかの視線を反射して光ってみえたので、少しドキリとする。
小声で「出ろ」と言っている。
え? ちょっと早くない? と千尋が戸惑っていると、坂城が千尋の腕をむんずと掴み、引き寄せて、舞台へと押し出した。
途端に、キャストたちの周囲の声が消えて、スポットライトが中央を抜いた。
一瞬、千尋は戸惑った。
展開が早すぎる。十青くん、間違えたの? などと困惑している間に、中央でスポットライトに抜かれた人物は、レイでも、番人でもないことに気がついた。
こちらを向いて戸惑うように立っている、男――
森本武臣だ。
千尋の胸に衝撃が走って、鼓動が、激しく、高鳴り始めた。
胸の奥にしびれたような感触が走る。
衝動的に逃げたいような気持ちに襲われたが、次の瞬間、周りは全て森本の見方なのだと気がついた。彼に抱きつきたいような衝動にも襲われたが、それもするわけにはいかず、千尋は舞台中央に抜かれたスポットライトの明かりに浮かぶ森本をみつめながら、立ちすくんだ。
森本は、眼差しを千尋に向けている。
背を客席の方に向け、舞台袖から出てきた千尋に向かって立っているので、スポットライトを背中から受けているせいか、表情がはっきりしなかった。でも、どこか瞳におびえたような色が見える。
そして、強い決心の色も。
思わず千尋は振りかえった。しかし振りかえって目があった坂城に睨み返され、また、視線を戻した。
客席も、舞台も、しんと静まり返っている。
何を言ったものかという焦りが、胸の中にじわじわと沸いてきて、何か言わなければ、と思った時、森本が静かにため息をついた。
千尋をじっと見据えると、
「良き時も」
と口を開いた。
「良き時も、悪しき時も、
富める時も、貧しき時も、
病める時も、健やかなる時も」
そう森本がゆっくりと、はっきりとした口調で言葉を続け、そこで一度言葉を切って、ホッとしたように表情を緩めた。「病める時も」で、結婚式の誓約の言葉だと千尋は気付いたが、久しぶりに見た森本のホッとした顔に、千尋はドキリとする。
森本は続けた。
「たとえどのようなことが起ころうとも」
森本が一語一語力強く、言って言葉を切り、千尋を見つめた。
薄暗い舞台の上で、スポットライトが妙にまぶしい。千尋は、頭の中で、池野の父と、それから母親との結婚式での誓いの言葉を思い出していた。
死が二人を分かつまで―――そう続くのだ。
唇が微かにしびれた。
「俺たちの予定した結婚式には、この言葉はなかったけれど、お前と結婚するって決めた時から、俺は、お前の過去も、苦しみも、全部ひきうけようって決めたんだ。お前には言わなかったけど、結構な覚悟だったんだ。お前、知らないだろう?」
千尋の唇がふるると震えて、彼女は慌てて手で口元を抑えた。
「それなのにお前は、俺を放り出して行くのか?」
千尋は森本の言葉に、両手で口元を抑え、ギュッと目をつぶった。
「坂城さん!」
唐突に千尋は叫んだ。
叫んで、やや間があって、「おう。」と後ろから返事が飛んできた。
「坂城さん、ひどい!」
千尋が大きい声ではっきりそう言うと、やや間があって、同じような声の口調で、
「ひどかねえよ」
坂城の声が飛んできた。
千尋は坂城の方を振りかえり、
「なんでこんなことするの? ひどいじゃない、ひどい」
「ひどかねえよ」
坂城はまた、そう言葉を継いだ。舞台の端でスポットライトの明かりが届かない位置にいるので、表情がよく読み取れない。
「周りがみんな不幸になる、俺が一番ひどいんだよ。お前らくらい、幸せになれ。」
千尋は衣装のスカートを両手で握りしめた。
「もう舞台、出ないわよ!」
千尋が震える声でそう言うと、やや間があって、
「許してやらあ。」
と声が返ってきた。
一瞬意識が遠くなった。それから、うつむいて衣装のスカートを握りしめると、ゆっくりと森本に振りかえった。
「森本さん。」
千尋が呼びかけると、スポットライトの逆光の中、森本が「はい」と返事をする。その「はい。」があまりに普通の「はい。」なので、千尋は少し拍子抜けした感じになりながら、「あたし」と言葉を継いだ。
おそるおそる森本を見上げて、おそるおそる口を開いた。
「あたし、ひどい女なのよ。あたし、すっごいひどい女なの。エイジが死んだのも、きっとあたしのせい、その後、逃げて、一人だけ幸せになろうなろうとして、都合良く記憶喪失になって」
「知ってるよ」
「知ってる? ね、そうでしょう? あたしがいなければ、柴野さんだって死なずにすんだ。」
「お前がいなけりゃ、柴野さんは、エイジに出会わなかったよ。」
千尋は森本の顔を見上げた。
「俺、柴野さんは、エイジくんと出会って、不幸と同じくらい、幸せだったと思うけどな。」
千尋は森本の顔をみつめた。
気まずさに、うつむいて、首を振る。
「そんなことない。」
「本当に?」
千尋は唇をかんだ。
「あたしはずるい。」
「ずるくないよ。」
「ずるいわよ! いっつも、都合が悪くなると、逃げてたのよ。いっつも、いつだって。記憶喪失になったのだって、そうじゃない。そうやって、逃げて、逃げて、いつだって。」
「じゃあ」と森本は言葉を継いだ。千尋は「え?」と顔を上げると、
「ズルかった、そういうことにしておこう。」
森本の言葉に、千尋は思わず唇を噛んだ。それから、眉根を寄せて、
「過去形にしたって…」
「だからもう、逃げるのはよそう」
森本の言葉に、思わずビクリとする。
「俺から逃げるのはよせって。お前、今度は幸福から逃げようとしてるだけだよ。人の不幸をたくさん見て、自分だけ幸福になるのが恐いんだ。」
「ちがう」
千尋は首を横に振った。
「違わないよ。」
「森本さん、わかってない。」
「わかってるよ。」
「あたし、ひどいことしたのよ。すっごい、ひどい女なの。だから、幸せになっちゃいけないのよ。」
「その分苦しんだだろう?」
「マグダラのマリアだったのよ。」
「知ってるよ。」
「婚約者放り出して、記憶喪失になって」
「知ってるって。」
「人の死を願ったことだってあるのに」
「それも」
「じゃあ、なんで!」
森本の顔は話ながら、どこか笑っている。それが千尋を余計混乱させた。
千尋には、森本はなぜ、今笑っているのかがよくわからない。
「その全部が今のお前で、そう言うお前と出会って、俺は、お前と生きていこうと思ったの。お前俺の話きいてる? 二人で探した過去だろう?」
千尋はスカートを握った手を、さらに固く握った。
ふいにうつむいた目から涙がこぼれて、はっとした。森本がスポットライトの中から抜け、歩み寄ってきた。見上げた森本の顔に、先ほどの笑顔はなかったが、彼は千尋の頭にポンポンと手をのせて、それから何かに気付いた、というような素振りを見せた。
口元に手を当てて、少し戸惑う素振りを見せ、
「『気付かなかったの、あの日は。あなたが本当は、何を、どう考えていたのか。』」
と言葉を継いだ。千尋は一瞬森本が何を言い出したのかわからなかったが、体の内側から、次のセリフがあふれてくる。
そうだ。『憂情の森』ラストの、シェレンのセリフだ。
森本は言葉を続けた。
「『でも、今日やっとわかったの。今日はじめて、やっと本当の』」
そこで森本は少し言いためらった。照れくさそうに笑う顔をみつめながら、千尋は首を傾げた。「次のセリフは、本当の、あなたに」と頭の中に浮かんだところで、森本が、突然千尋を抱きしめた。
「やっと君に、出会えた気がする。」
森本の肩越しに、スポットライトの光がまぶしい。
千尋は、スカートを握り締めた手を森本の背中に回すと、そのまましがみつくようにその体にまきつけた。
体から心があふれて、自分がどこにいるのかわからなくなりそうになりながら、森本の体をしっかりと、まるで自分の感覚をなくすまいとするように、彼の背中の服にしがみついて、抱きついた。
次の言葉を出そうとするのに、口は開いたまま、ただ涙ばかりがあふれてくる。
声はなかった。
ただ感情が、波のように押し寄せて、あふれてくるばかりだった。
千尋は一度、奥歯を強くかみ締めると、二、三度息継ぎをする。
「『ありがとう』」
震える声で次のセリフを言ったのは、千尋だった。
「『でももしかしたら、エレナは知っていたのかもしれないわね。知っていて、どうにもならなかったのかもしれない。』」
千尋がそう言うと、突然後ろから大きな声で、
「ブラーボウ!」
と叫んで、大きな拍手が一つ、パンパンパンと響いた。
坂城だ。
舞台のラストシーンでもないのに、周りから拍手が起こる。堰を切ったように、涙があふれた。涙ばかり、声が、出ない。大きくあえいで、声は、出ない。
千尋の頭の中に次々と、最初に記憶を失ってからの日々が蘇る。
少しずつ、少しずつ、取り戻して、最後に振り出しに戻った。
振り出しに戻って、一度に加速した。
長かった、遠かった、あの日から、――いつから? いったいいつから、ここにたどりついたのだろう。
今この時のためなら、過去のすべてが許されると思った。
過去のすべてが、報われると思った。
森本の胸に顔をうずめて泣く千尋の後ろで、坂城が、「ト―セー!」と客席後ろに叫んだ。
「中央消して舞台と客席のライトつけろや。お前も出て来い! みんな舞台あがれ!」
森本の声に、照明がともされ、客席と舞台が明るくなった。どこからともなく安堵のため息がもれ、劇団員やスタッフが舞台に駆け足で集まってくる。
「オラオラ、椅子持って両脇にすわんだよ。中央に机もってきな、机!」
舞台端から団員に指示をとばす坂城に、千尋が森本の胸から顔をあげキョトンとした顔を見せた。
千尋が涙声で、
「坂城さん、何するの?」
と尋ねると、
「何言ってんだよ、お前らの結婚式に決まってんだろう?」
そう答えた。
坂本十青が調整室から客席に出て舞台に歩み寄りながら、
「坂城さんが、神父やるんですか?」
と尋ねた。
「おおよ、俺じゃなきゃ、誰がやるんだ。」
「えー?、いつ風呂入ったんです?」
周りからドッと笑いが起こった。
「純自然児の俺が神父やるんだから、神もお喜びだよ。」
それでまた笑いが起こった。
坂城は、舞台端から、森本と千尋のそばに歩み寄った。そして、森本の顔を見上げると、
「おいしいな、今度そのネタゆずれや。」
と笑ってみせた。すると森本は苦笑して、
「ネタじゃねえよ。」
言葉を返した。
坂城はふんと鼻で笑ってみせた。
「おう、千尋、おう、お前、今の感想言ってみろ。」
千尋の頭をこづきながら坂城がそう言うと、千尋はズルズルと鼻をならして、涙声で、
「坂城さん。」
と言葉をかけた。
「ん?」
坂城が耳を寄せると、
「あたし、本当に嬉しい時って、すっごく笑えるものだと思ってた。」
千尋がそう言うと、坂城は嬉しそうに笑い、彼女の髪をぐしゃぐしゃとやらせた。
「さあ、結婚式だあ! お前らも並べえ!」
坂城は、用意された机の前に歩を進めた。その前で団員の一人が「森本さん、千尋ちゃん!」と言って、手でおいでおいでしている。
それは粗末なバージンロードだった。
花婿に手渡す父もいない、絨毯さえ、ひかれていなかった。
花嫁の涙はしばらく止まりそうになかったし、神父の頭は相変わらずぐちゃぐちゃだった。
横から森本がそっと「今度ちゃんとまともな式あげてやるからな」と耳打ちする。
千尋が笑う。
そして、神に感謝する。
お母さん、と心の中で呼びかける。
もう一人じゃないよ、とつぶやいてみる。
もう、一人じゃないよ――――
エピローグ
七月二日に開始された劇団絶対零度の『憂情の森』第三回公演は、最初池野千尋主演の形で上演されたが、予想以上の好評で、そのため千尋はわずか一週間にして主役から降りなければならなくなった。
まだ事件が生々しい上に、オーナーである園山隆史の進退に関わるという少し複雑な事情からだった。
幸い、柴野の一件は被疑者が死亡しているために、マスコミでは小さく取り扱われ、園山との関係まで表沙汰にならなかったものの、やはり身内に殺人者がいるというのは、それがどういう経緯で、どんな人間的感情があったにせよ、スキャンダルでしかなかった。さらに、殺されかかった千尋が、その人の主催する舞台で主役を勤めている、というのは、万が一全てが知られた時にのっぴきならないことになる。せっかく得た平穏なのに、本人自らそれを壊す必要もなく、坂城自身もスキャンダルを得てまで話題を呼びたいとは思わなかった。
それぞれの判断で、主役は静かに交代され、千尋は森本の経営する「ミル」へと戻って行った。
『憂情の森』そのものは第三回公演が終了し、再演未定のまま、一ヶ月の幕を降ろした。
「また機会があったらやろうな」と坂城は言ったが、千尋は、「坂城さんは、榎木さんと組むのが一番息があってるよ」などと言って、二度と舞台に上がる意志のないことを遠まわしに示した。
そして、八月の始めの蒸し暑い頃、柴野有里の納骨式がひっそりと行われた。
柴野の家の墓に入れることは、母親が強く辞したので、なかったのである。また、まさか池野の墓に入れるわけにはいかず、柴野有里の母親の実姉にあたる、園山の母の申し出で、母親の実家の墓がある、そのそばに、彼女の墓を別に建てることにした――と、園山から、坂城経由でこの経緯が伝えられた。
千尋はとても柴野の家のものには会えないだろうが、もしよかったら納骨が済んだ後にでも都内某所にある墓所に参ってやってくれないか、と、――これは園山隆史本人が電話で森本に申し入れた。
電話を切った森本は、千尋にそのことを伝えた。
それで千尋は、坂城もまだだというので、森本と三人で連れ立って、墓に参ることにしたのだ。
それは蒸し暑い日で、蝉の鳴き声が妙にうるさかった。
境内の裏にある墓所へと歩を進めると、柴野の真新しい墓は比較的広い墓所の一角に、場所を裂いたという感じで――、いや、その家の墓の中に、別の名の墓が入り込んだ、と言っても過言ではないほどの近さで、設けられていた。
この暑いのに、前に備えられた花が真新しい。納骨式からさほど日が経っていないのだろう。千尋と森本、それから坂城は、三人ともが黒の喪服に身を包んで、線香とろうそくをそなえた。
三人、目を閉じて静かに手をあわせながら、背中にじっとり汗のにじむのを感じた。
千尋が目を開けると、ろうそくの明かりが目に入った。
厳しい暑さと、ろうそくの炎の色が、つい、と、あの日を思い起させて、慌てて目を閉じる。
「行こうか。」
と森本の声に、「え? もう?」と千尋は思ったが、口にせず、心残りのまま墓を離れた。
千尋の前を歩く二人が、世間話を始める。
坂城の仕事の話らしい。
千尋はこっそり、柴野の墓を振りかえった。
暑さで揺らぐ大気の中に、また、あの日の炎がゆらりと浮かぶ。
慌てて、前を向いた。
あの日、柴野はなぜ、あの場所へ千尋を連れて、あんな話をしたのか。
それは、葛西刑事にもきかれたことだった。
今ならわかる、と千尋は思うのだ。
柴野はあそこで死にたかった、それは、誰にも明白だった。でも、そこに千尋が必要だったのだ。
一番、憎むべき千尋が、誰よりも、彼女を理解できた。
それは柴野も知っていたことなのだ。
柴野はただ、残したかっただけなのだ。
そこで命を終える理由を――生きてきた証しを、誰かに理解されて、そして、残したかった。
記憶に―――
誰かの記憶の中に―――
だから、と、千尋は思った。
忘れない――。
もう決して、忘れない、と。
夏の日差しに、汗ばんだ手をみつめる。それから、ゆっくりと顔を被った。
たくさんの命が、私の中で生きている。
記憶の中――そして、体の中に――
今も、そして、これからも、生き続ける。
命ある限り―――
完
あとがき
平成十年夏、新聞屋が新聞の支払いを自動振替に替えたために、映画の券を二枚くれた。七月九日、友人が休みをとれるというので、わざわざ京都から大阪梅田まででかけていくことにした。上映期間があまり長くないので、とりあえずその友人と行くことになった――というか、ただ券くれても行きたいと思った映画以外にはガンとして行かない私が、その時に限って行く気になったのは、実はキタに酒を飲みに行くことが一番の目的で、映画はまあ、ついでだったのだ。
という出だしで書き始めるとたいへん失礼なのだが、それが、大森一樹監督の「June Bride」だった。
でまた趣味の悪いことに、その後行った酒の席で、あそこはどうの、ここはどうのと、映画の茶かし合い合戦になってしまい、「ぃよーし、書きなおしたろかあ? パロディ書いちゃろかあ!?」「おお、書いてまえ、書いてまええ!!」と勢いづき、友人と別れた後、酔った勢いで帰りの電車の中でホロホロと話を組みたて直したのが、この「June Bride」だったのである。
真面目な人や映画のスタッフ・出演者本人たちがきいたら大いに怒りそうなエピソードで、もしかしたら書かない方が良かったかも、とも思うが、これぐらいラフなノリでいかないと、かえって「パロディの粋さ」がない。「てめえ、こんな話はいかんぜよ」と青筋立てて、怒りながら作ったとあっては、なんかひどい不粋じゃないか。
ということで、本当のところをデフォルメしないで、書いてみました。
ホームページのトップページ解説には、「パロディ的試作」というふうにお断りしていますが、どちらかというと、「批評小説」と言った方がいいかもしれない。本来の批評小説というのは、作品の中の人物や語りが直接、作品を批評するものなので、これはちょっと正しい言い方ではないのだけれど、姿勢は同じなので、それでよろしいかと思います。
私は以前、連載中副題にも使った『霧中』という、高校時代に書いた小説で、記憶喪失ものを取り扱ったことがあるので、映画を見ている時にも、私の中では、「あ、『霧中的作品』」と、つい思ってしまい、一度書いたことがある故に、「あんなに簡単に記憶を失うものか?」と思い、また、「あんなに簡単に記憶って戻るものか?」と大いに疑問を抱き、今回の夏野版では、その疑問をストレートに出して、その部分で大きく改変させました。それが大筋での改変であるなら、小さい所の改変は、随所に盛り込んであります。ほとんど、「え? それってちょっと…」というのが原因になって改変されております。
執筆期間としては、その映画を見終わってほぼすぐの時期に書き始め、八月中に細かいところを練りながら、いろいろ調査を進めていきましたが、保険金の資料だけがなかなか手に入らず、ほとんど見切り発車で進んだところ、それから和歌山保険金事件を見ているうちにボロボロ資料がテレビの画面からこぼれて来まして、ようやくなんとか筋が通せたという感じです。
ホームページの立ち上げが、確か九月に決まり、そこで、十月頃に一度執筆の手を休めました。それが六章まで。再開したのが、ホームページ七章更新時の七月からですから、たぶん、ここの間でトーンが大きく変わっているのではないでしょうか。足掛け一年九ヶ月、こんなに時間をかけたのも、『霧中』以来です。
何度も練りなおした「出来あがり原稿」ではなく、締め切り前に書いた「ほぼ生原稿」なので、おそらく終了後に、間延びしたところ、急いだところは手を加えると思います。でもまあ、よくもここまで書けたもんだ、と書いた本人がびっくりしています。
まさか完成するなんて、とは思いますが、一つ書き上げて、通しで実感した(学んだ)ことは、他人の作品をベースに使うというのは、かなり精神的に楽なんだ、ということでした。皆パクリやるはずですよね。妙に納得でした。「箱の中」や「霧中」系の作品なんて、中盤入る前はたいがい胃をやられてゲーゲーなんですよ。
ものを生み出すってたいへんだ。
最後に、BGM。
書くときに使った主用BGMは、前半は様々でしたが、後半はほとんど、玉置浩二のアルバム「ワインレッドの心」でした。「箱の中」はTHE BOOMの「極東サンバ」でノリノリで書いてまして、皆にどういう神経してるの?と言われたんですが、一応今回はOKでしょう。「どんなにかなしーいーこぉとぉもぉ、わたーしーにー、つたーえーてー、うう、こんな哀しいことがあっていいのかしら!?」とか言いながら書いていました。だいたい、アルバムの中に内容とニアミスソングが書いてる本人も気付かない間に混じっているものですが、今回は、三曲目の「Friend」でしたね。千尋→柴野の関係(本当は男女の歌だけど)。
ちなみに作中詞「SOMETIME」は話の中では男の人の歌う曲でしたが、私の中では、宇多田ヒカルさんが歌った時をイメージして書いてました。玉置さんでも合うかもしれませんね。
ということで、いかがでしたでしょうか、「June Bride」。
敢えてキーワードを上げるなら、「理解」でしょうか。
本当は「箱の中」の後の第一作目の長編新作なんだけど、新作という感じもしなかったし、さりとてパロディを書いている、という感じもあまりしませんでした。
欲を言うならもう少し丁寧に書きたかった。
これの改稿はすごいものになっているかもしれません。
また(笑)、お会いしましょう。
平成十二年三月十四日
咲花実李